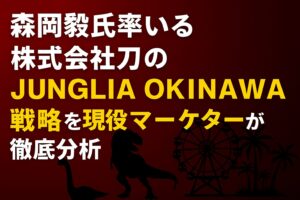2025年5月4日
Contents
はじめに:なぜ中小企業のマーケティングは頑張ってもうまくいかないのか?
中小企業のマーケティングが思うような成果を上げられない最大の理由は、
「施策が単発的になってしまっている」という現状にあります。
私が外部CMOとして100社を超える中小企業のマーケティング支援を行ってきた経験から言えることは、本来あるべきマーケティングの姿とは
「目的を定め、その目的に対して戦略を決め、決めた戦略に対して逆算的に施策を打っていく」形であるということです。
しかし、多くの中小企業では、この「マーケティング設計」の難易度が高いと感じられ、結果として頑張っても成果に結びつかないケースが非常に多いのが現状です。
確かに、「インスタグラムでバズった」「TikTokで売上が一気に伸びた」といった成功パターンもありますが、これらは「偶発的」なものであり、再現性に乏しいのです。
私が数多くの現場で見てきたのは、「動画は伸びたけれど売上につながらなかった」という残念な結末です。
私はマーケティングを「売れる仕組みづくり」と定義しています。
それは偶然生まれるものではなく、意図的に「設計」していくものなのです。

本記事では、限られたリソースの中でも成果を上げられる、実践的な「売れる仕組みの作り方」についてお話しします。

なぜ中小企業には「売れる仕組み」が必要なのか?
単発施策だけでは売上が安定しない理由
「一度やってよかったけど、再現性がないからまたできない」という状況は、事業の安定性を大きく損なうものです。

私が支援した製造業の企業では、展示会で一時的に注目を集めたものの、その後の施策展開ができず、結果として売上が元に戻ってしまったという苦い経験がありました。
構造的・戦略的に売上が上がる仕組みを構築できれば、こうした「一発勝負」から脱却し、安定した事業基盤を築くことができます。
売上=市場×単価×顧客数×プレファレンス×頻度×認知|成功企業はここを意図的に設計している
USJをV字回復させたことで有名なマーケターの森岡氏も指摘しているように、売上は複数の要素から構成されています。
特に「認知」「頻度」「単価」といった要素は比較的コントロールしやすく、成功している企業はこれらを意図的に設計しています。

私が支援したEC事業の会社では、これらの要素を意図的に設計することで、売上を前年比150%まで伸ばすことに成功しました。
特に顧客の「頻度」に着目した定期購入モデルの構築がブレイクスルーとなったのです。
「売れる仕組み」がないとどんな落とし穴にハマるか?
売れる仕組みがないと、「何をやったらいいのかわからない手探り状態」に陥りがちです。
マーケティング戦略とは「戦いを略する(設計する)」ことであり、これがないと地図なき戦いを単発的に仕掛けていくことになります。
こうした状況では、マーケティング担当者やチームが疲弊し、
「一度やってダメだったからもうマーケティングはダメなのかな」「自社に合わないのかな」といった誤った判断に至ることも珍しくありません。
特に中小企業は、人材・予算・ノウハウといったリソースが限られている中で成果を上げる必要があります。
売れる仕組みを作る戦略マーケティングの基本
マーケティングは「商品を売るテクニック」ではない
マーケティングは単なる「商品を売るためのテクニック」ではありません。
私の専門分野である戦略マーケティングでは、「誰に(WHO)、何を(WHAT)、どうやって(HOW)届けるか」という視点が極めて重要です。
この基本的なフレームワークがあることで、チーム内での共有が容易になり、現在実施している施策がどのターゲットに対して何を売っているのかを明確にできます。
また、仮に施策が想定した成果を上げられなかった場合でも、次への改善策を打ちやすくなります。
WHO・WHAT・HOWの視点がなぜ必要か?
私がマーケティングのインハウス化を支援してきた経験から言えることは、このフレームワークがチーム内の「共通言語」となり、マーケティングの「俗人化」を防ぐ効果があるということです。
一人の担当者だけがマーケティングのやり方を感覚的に理解している状態では、その人が退職したら何もできなくなるという危険性があります。
フレームワークに落とし込むことで、チーム内での共有がしやすくなり、インハウス化も進めやすくなります。
一貫性がなければ、施策も結果もバラバラになる
戦略的一貫性のないマーケティングは、まるで方向性のない船のようなものです。
ある企業では「とりあえず広告を出そう」「とりあえずSNSをやろう」という状態から、
WHO・WHAT・HOWのフレームワークを導入したことで、目標達成までの道筋が明確になり、予算の無駄遣いが大幅に減少しました。
一貫性のあるマーケティング戦略は、リソースの最適配分を可能にし、結果として売上の安定化と成長に寄与するのです。
現役マーケターが教える!売れる仕組み設計3ステップ
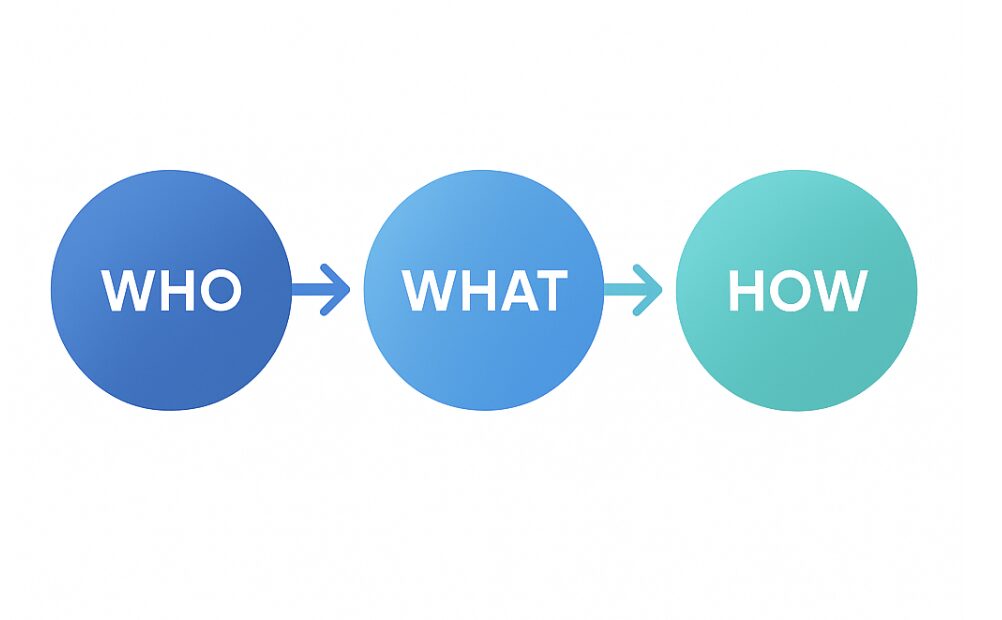
私の会社では現在、マーケティング戦略を考えてくれるAIサービス「MyMarketer(マイマーケター)」を開発していますが、その戦略策定には実に12のステップがあります。
しかし本記事では、特に重要な3つのステップに絞ってお伝えします。
Step1|ターゲット(WHO)を具体的に絞り込む
まず第一に「誰に」というターゲット設定から始めることが重要です。
なぜなら、ターゲットによって提供すべき価値が大きく変わるからです。
例えば、同じファミレスでも、女子高生をターゲットにするか、サラリーマンをターゲットにするかで、提供すべきメニューや店内環境は全く異なります。
女子高生であれば甘いデザートやドリンクバーが重要かもしれませんが、サラリーマンであれば商談がしやすい環境や、素早く提供されるランチメニューが求められるでしょう。
ターゲット設定では、「より広い範囲を取りに行く」ことを意識し、無意味にターゲットを狭めないことが重要です。
また、自社と相性がよく、LTV(顧客生涯価値)が高い顧客層を見極めることも大切です。
Step2|顧客に響く提供価値(WHAT)を定義する
ターゲットが決まったら、次は「どんな価値を提供するか」を考えます。
これは「ドリルと穴」の例えでよく説明されるポイントです。
ドリルを買う人は実際にはドリル自体ではなく「穴」という結果を求めているのと同様に、お客様が本当に求めている「本質的価値」を見極める必要があります。

私が支援したクライアントでは、「商品の機能」を売りにしていましたが、実際に顧客が求めていたのは「使用後の安心感」でした。この「価値」の再定義により、マーケティングメッセージを変更したところ、コンバージョン率が35%向上したという事例があります。
この本質的価値を絞り込み、設定することで、「やるべきこと・やらないべきこと」が明確になっていきます。
Step3|効果的な施策(HOW)を戦略的に設計する
最後に、定めた価値をどのように伝えていくかを考えます。
この「HOW」の部分は、一般的には4P戦略(Product・Price・Place・Promotion)でまとめられることが多いですが、必ずしもこの枠組みに当てはまらないケースもあります。
重要なのは、Step2で定めた「WHAT(価値)」をいかに低減させずに効率的に伝えることができるかという点です。
これを念頭に置いて施策を設計することで、ターゲットに対して価値が100%の状態で伝わるようになります。
広告やプロモーション、プロダクトなど、目に見えて顧客のもとに届くものはすべて「HOW」の戦術的な部分に含まれます。

私が支援した企業では、この「HOW」の部分を徹底的に見直したことで、広告費を30%削減しながらも、売上を20%増加させることに成功しました。
よくある失敗パターンと「売れる仕組み」成功企業の違い
「とりあえず広告」「とりあえずSNS」の末路
「とりあえず広告を出そう」「この強みでいこう」「とりあえず認知を広めよう」「とりあえずSNSをやろう」といった戦略なき行動は、残念ながら失敗する可能性が高いです。
私が見てきた失敗事例の中で最も多いのが、このような「とりあえず」型のマーケティングです。

ある企業では年間500万円の広告予算を「とりあえず出そう」という考えで運用していましたが、成果が出ないまま予算を消化してしまいました。
一方、戦略的アプローチに切り替えた後は、同じ予算で3倍のリターンを得ることができたのです。
ターゲット不明確・価値不明確・施策バラバラが招く失敗
戦略のない状態では、ターゲットが不明確、提供価値が不明確、そして施策もバラバラになりがちです。
これでは、各施策の効果を測定・管理することも難しくなります。
「何をやったんだっけ?」「売上は伸びた気がする」「変わらなかった気がする」「次は何をしよう?」という循環に陥り、結局は時間とリソースを浪費するだけになってしまいます。
成功企業は何をどう設計しているのか?(具体事例紹介)
私がコンサルティングを行った製造業の企業(従業員30名)では、WHO・WHAT・HOWのフレームワークを導入した結果、売上が2年で2倍に成長しました。
彼らは以下のように設計しました。
この明確な設計により、広告費は従来の70%に削減しながらも、ターゲット業界のシェアを3倍に拡大することができたのです。
売れる仕組みを持つと得られる3つの成果
無駄な広告費を削減できる
明確な戦略に基づいたマーケティングは、無駄な広告費を大幅に削減します。

私のクライアント企業では、戦略的マーケティングの導入後、広告費を40%削減しながらも売上を25%向上させることができました。
「誰に」「何を」伝えるべきかが明確になることで、広告の効率が劇的に改善するのです。
営業・集客の効率が劇的に上がる
戦略的マーケティングにより、営業活動や集客の効率も大きく向上します。

とある企業では、営業チームが使う資料や訴求ポイントを戦略に合わせて統一した結果、商談成約率が従来の15%から32%へと倍増しました。
「やるべきこと」が明確になることで、チーム全体の効率が高まるのです。
売上が安定し、事業成長の再現性が高まる
最も重要な成果は、売上の安定と成長の再現性です。
「売れる仕組み」を持つことで、一時的なバズや偶発的な成功に頼らない、持続可能な事業成長が可能になります。

私がコンサルティングを行った企業では、季節変動が大きかった売上が、戦略的マーケティングの導入後は年間を通して安定するようになり、計画的な投資や人材採用が可能になりました。
また、単発施策だけでなく、戦略が明確であることで、無駄な人的リソースの削減や、メンタル面での負担軽減にもつながります。
闇に向かって人がどこまで進み続けられるか分からない状態から脱却し、より効率的かつ持続可能な組織運営が可能になるのです。
まとめ|小手先ではなく「仕組み」で勝つ時代へ
リソースの限られている中小企業こそ、マーケティング戦略が必要です。
WHO・WHAT・HOWといったマーケティング・フレームワークを最大限活用し、小手先の対応ではなく「仕組み」で勝っていく時代になっています。
単純に時間と人的リソースを莫大に投入するのではなく、正しい設計で逆算的に売上を伸ばし、構造的に選ばれるブランドを作ることが重要です。
「売れる仕組みづくり」こそ、中小企業がまず取り組むべきファーストステップなのです。
MyMarketerは、こうした私の考えを形にしたAIマーケティング戦略立案サービスです。
従来、外部コンサルティング企業に依頼すると月200万円以上、優秀なマーケター採用には月給65万円+採用費約270万円もかかっていたマーケティング戦略立案が、月額たった5万円で利用できます。
ぜひ、貴社の「売れる仕組みづくり」にお役立てください。

筆者プロフィール
山本 至人
株式会社WHAT 代表取締役。
法政大学法学部卒業。映像制作事業やD2Cアパレルブランドなど複数の新規事業立ち上げにCMOとして携わる。2023年に株式会社WHAT設立。外部CMOとして多くの企業のマーケティング支援を実施。東京大学松尾研AI経営修了。